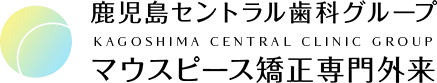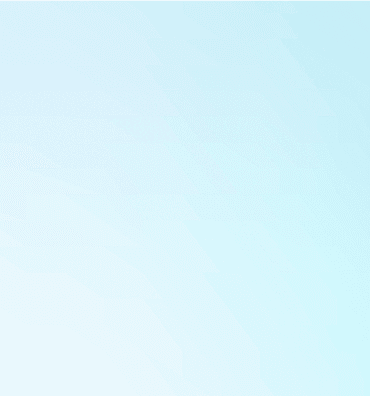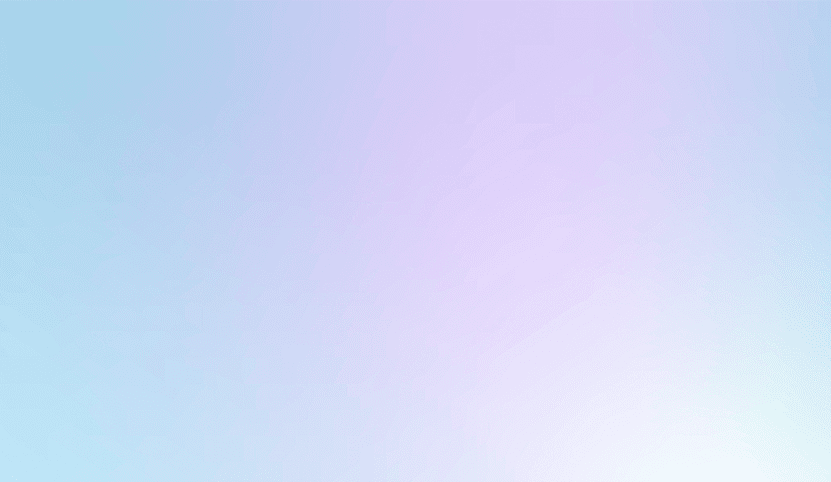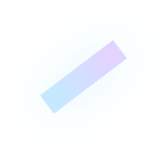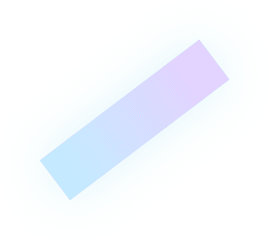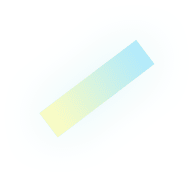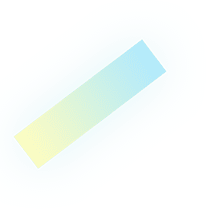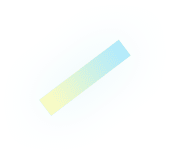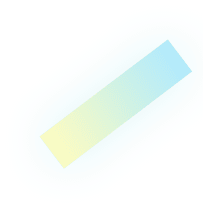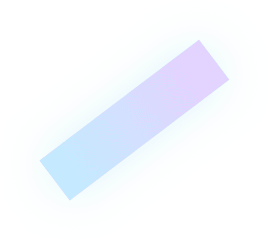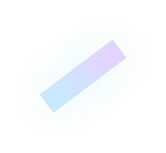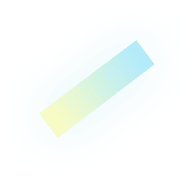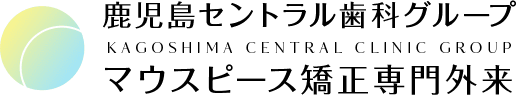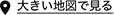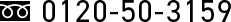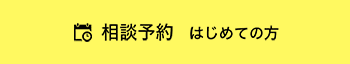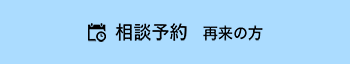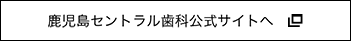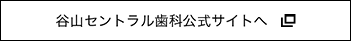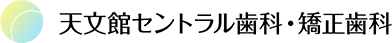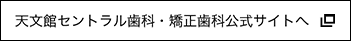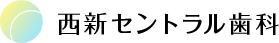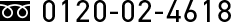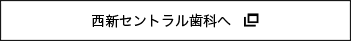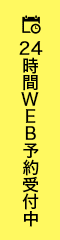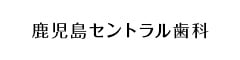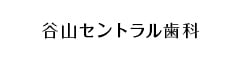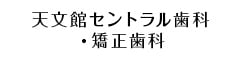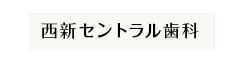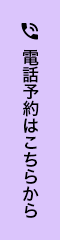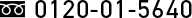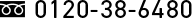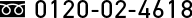矯正の医療費控除、最大いくら戻る?申請方法も完全解説
歯並びや噛み合わせを整える歯科矯正は、美しい口元を手に入れるだけでなく、歯の健康を守るためにも重要です。しかし、矯正治療には高額な費用がかかるため、治療を検討される患者さまにとって、費用負担は大きな課題となるでしょう。そこで活用したいのが「医療費控除」です。矯正治療の費用が医療費控除の対象となる場合、所得税の一部が還付され、経済的負担を軽減できます。本記事では、矯正治療の医療費控除について、最大いくら戻るのか、具体的な計算例を交えながら解説し、申請方法まで詳しくご紹介します。賢く制度を活用し、負担を軽くしながら適切な矯正治療を受けるための参考にしてください。
◎そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の負担を軽減できる税制優遇制度です。確定申告を行うことで、支払った医療費の一部が所得控除の対象となり、結果として税金が還付される可能性があります。
◎医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象額は、以下の計算式で求められます。
(年間の医療費 – 保険金などで補填される額) – 10万円または所得の5%のいずれか低い方
例えば、年間の医療費が50万円で、保険金による補填がなかった場合、控除対象額は40万円(50万円 – 10万円)となります。
◎矯正治療の医療費控除の条件
矯正治療が医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的によって異なります。
【対象となる場合】
・噛み合わせの改善を目的とする治療(機能的な問題を解決するため)
・成長過程にあるお子さまの歯並びを整える治療
【対象とならない場合】
・美容目的の矯正治療(審美的な理由のみで行う場合)
このように、治療目的が「機能回復」や「噛み合わせ改善」であることが重要なポイントとなります。現実的には、ほとんどの症例でこのポイントが当てはまります。
▼矯正の医療費控除で最大いくら戻るか?
矯正治療で実際にどれくらいの税金が還付されるのか、具体例を挙げて説明します。これはあくまでシミュレーションであるため、参考程度にお考えください。
例1:年収500万円の方が80万円の矯正治療を受けた場合
控除対象額 = 80万円 – 10万円 = 70万円
所得税率(年収500万円の場合) = 20%
還付額 = 70万円 × 20% = 14万円
このケースでは、14万円の税金が還付される計算になります。
例2:年収800万円の方が100万円の矯正治療を受けた場合
控除対象額 = 100万円 – 10万円 = 90万円
所得税率(年収800万円の場合) = 23%
還付額 = 90万円 × 23% = 20.7万円
このように、治療費が高額になるほど、また所得税率が高いほど、還付額も増える傾向にあります。
なお、住民税の軽減効果もあり、控除額の10%(最大4万円)が住民税から差し引かれるため、さらに負担が軽減されます。
▼矯正の医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。以下の手順で申請を行います。
1.必要な書類を準備する
・矯正治療費の領収書(提出を求められた場合のためにも原本を保管)
・矯正治療の診断書(提出を求められた場合のみ必要)
・医療費控除の明細書(国税庁のフォーマットに従う)
・源泉徴収票(会社員の場合、勤務先から発行されるもの)
・交通費の記録(通院にかかった公共交通機関の領収書や記録)
2.確定申告書を作成する
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると便利です。必要事項を入力し、医療費控除の欄に治療費を記入します。また、e-Taxを活用すると、オンライン上で申請が完了し、還付の処理もスムーズになります。
3.税務署へ提出する
確定申告書と必要書類を準備したら、税務署へ提出します。提出方法は以下の3つです。
電子申告(e-Tax):オンラインで提出可能。還付までの期間が短縮されるメリットがあります。
郵送:書類を税務署へ郵送。必要書類の漏れがないようにチェックしましょう。
税務署へ直接提出:窓口で申請。直接職員に確認しながら提出できるため、確実な申請が可能です。
申告後、審査を経て還付金が指定の口座に振り込まれます。通常、申告後1~2ヶ月程度で還付金が支給されますが、申告時期や処理状況によって異なる場合があります。
▼矯正歯科の医療費控除の注意点
矯正治療の医療費控除を申請する際には、いくつかの注意点があります。まず、治療目的が医療的に認められるかどうかが重要です。美容目的での矯正治療は対象外となるため、診断書などで「機能的な問題の改善を目的としている」ことを明確に証明する必要があります。また、領収書の管理も大切です。確定申告時には領収書の原本提出は不要ですが、税務署からの確認が入る可能性があるため、5年間は保管しておくのが安心です。さらに、通院にかかった交通費も医療費控除の対象になります。公共交通機関を利用した場合、日付や金額を記録しておきましょう。これらのポイントを押さえて、スムーズな申請を目指しましょう。
▼まとめ
今回は、矯正歯科の費用の医療費控除について解説しました。矯正治療は決して安いものではありませんが、医療費控除を活用することで税金の負担を軽減できます。噛み合わせの改善や機能的な問題を解決する矯正治療であれば、医療費控除の対象となる可能性が高いため、治療費を支払った際は忘れずに確定申告を行いましょう。控除額は年収や治療費によって異なりますが、数万円から20万円以上の還付を受けられる場合もあります。申請には領収書や診断書などの書類が必要となるため、治療を受ける際には事前に準備しておくことをおすすめします。制度を賢く活用し、少しでも経済的負担を軽くしながら、健康な歯並びを手に入れましょう。